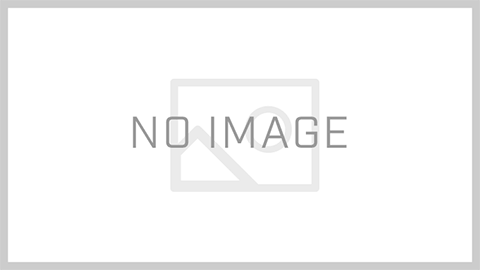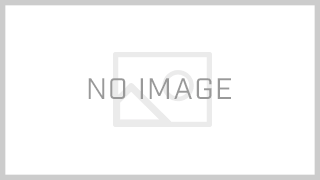2025年3月第3週(3月16日〜22日)は、世界の株式市場に影響を与える様々な経済ニュースが飛び交いました。日本発の話題から米国の金融政策、中国の政策動向、新興国のサプライズまで、個人投資家が注目すべき7つのトピックを厳選して解説します。それぞれ**「なぜ株に影響したのか」「何に注目すべきか」**を投資家目線で掘り下げます。
1. FRB、利下げ示唆で株式市場を支援 – 3月FOMC据え置きとパウエル発言
米連邦準備制度理事会(FRB)は3月19日まで開催の連邦公開市場委員会(FOMC)で、市場予想通り政策金利の据え置きを決定しました。インフレ鈍化傾向を受けて今年は「適切な時期」に利下げへ方針転換する可能性が示唆されており、パウエルFRB議長の会見内容はハト派寄りと受け止められました。特にパウエル氏が「関税による物価上昇への影響評価は時期尚早」と発言し、利上げで景気を冷やすリスクに慎重な姿勢を見せたことが好感されました。
この結果、米国株式市場はFOMC後に反発し、主要指数がそろって上昇しました。年内の利下げ期待は根強く、FF金利先物市場では**「6月までに0.25%利下げ開始」**との織り込みが6割超とされています。投資家にとって注目ポイントは、今後の経済指標次第でFRBがどこまで利下げに踏み切るかです。インフレ動向や雇用指標が利下げ余地を裏付けるか、またパウエル議長が市場の利下げ期待に寄り添う発言を続けるかが、株式市場の方向性に影響を与えるでしょう。
2. 米中関税「柔軟対応」で貿易戦争懸念後退 – トランプ発言が市場安心感

トランプ米大統領は関税発動を巡り柔軟姿勢を示し、交渉進展への期待が高まった。
3月下旬に控える米中双方の追加関税発動をめぐり、トランプ米大統領が**「柔軟に対応する」**と発言しました。またライトハイザー通商代表が来週に中国側と協議すると明かしたことで、4月初めに予定されていた報復関税の影響への懸念が和らいだと報じられています。このニュースを受け、長引く米中貿易戦争が軟着陸に向かうとの見方が広がり、株式市場ではリスクオフ姿勢が後退しました。
貿易摩擦懸念の緩和は特に輸出関連株や製造業セクターに追い風となりました。一方で、同じタイミングで米政府は次世代戦闘機製造をボーイングに発注し、ロッキード・マーティンが受注を逃すといった動きも伝えられています。これらは防衛産業や個別企業の株価に明暗を分けましたが、より大きなテーマとしては米中対立リスクの後退が市場全体のセンチメントを改善させました。投資家は今後の米中交渉の進展や新たな関税措置の有無に注目する必要があります。貿易協議のポジティブな進捗は世界経済の先行き不透明感を和らげ、株式相場の押し上げ要因となるでしょう。
3. 日本のインフレ3%台が継続 – 日銀の追加利上げ観測じわり高まる

日本では2月の全国消費者物価指数(生鮮除くコアCPI)が前年同月比+3.0%と、市場予想(+2.9%)を上回りました。エネルギー料金の補助金再開で伸び率自体は1月から鈍化したものの、3ヶ月連続で3%台の高いインフレ率が維持されています。生鮮食品とエネルギーを除くコアコアCPIも+2.6%と伸びが加速し、物価上昇の基調が底堅いことを示しました。
この結果を受け、市場では日本銀行の追加利上げ観測がじわじわと高まっています。実際、日銀は同週の金融政策決定会合(3月19日)では現状維持としたものの、上田総裁は春闘賃上げや海外発リスクを見極め「利上げはデータ次第」との姿勢を示しています。高インフレが続けば7月にも追加利上げに踏み切るとの見方もあり、特に銀行株など金利上昇の恩恵を受けるセクターに物色が入りました。実際21日には日本のメガバンク株が上昇し、日経平均やTOPIXの上げを主導しています。一方、FOMC後の急速な円高進行で自動車株が軟調になる場面も見られ、為替動向には注意が必要です。投資家としては、日本のインフレ指標や賃金動向と合わせて、日銀の微妙なスタンス変化を注視することが求められます。物価高止まりが続くなら、超低金利政策の転換が現実味を帯び、日本株のセクターローテーションにも影響が及ぶでしょう。
4. バフェット、日本の商社株を追加購入 – 東京市場に「追い風」ムード
東京証券取引所の建物。米著名投資家ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイが日本の大手商社株への投資拡大を発表し、東京市場の投資家心理にプラス材料となった。
米国の投資会社バークシャー・ハサウェイが、日本の五大商社(伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物産、住友商事)に対する持ち株比率を約10%近くまで引き上げたことが明らかになりました。3月17日に提出された大量保有報告書によると、各社の持ち株比率はいずれも従来の約8%台から9%台へと数ポイント上昇しています(例:三井物産は8.09%→9.82%)。これはバークシャー副社長が昨年、各社と合意した**「持分比率上限の緩和(10%超への引き上げ)」**を受け、実際に買い増しを行った動きです。
このニュースは東京株式市場にとって大きなポジティブサプライズとなりました。発表翌日の3月18日には商社株がそろって急伸し、5社平均で約4%前後上昇しました。バフェットが日本株に引き続き強気姿勢を示したことで、海外投資家からの日本株見直し買いにもつながるとの期待が広がっています。背景には、商社株の堅実なキャッシュフローや低いバリュエーションに着目した長期投資戦略があり、**「バフェットのお墨付き」**が個人投資家にも安心感を与えました。今後の注目点は、バークシャーがさらに持ち株比率を引き上げるのか、そして他の日本株にも投資対象を広げる可能性があるかです。世界的な価値投資の巨人による資金流入は、日本市場全体の追い風となり得るため、関連ニュースから目が離せません。
5. 原油価格が2週連続上昇 – イラン制裁強化とOPEC+減産計画で供給懸念

米ノースダコタ州の油田で稼働するポンプジャック(揚油装置)。米国による対イラン制裁強化と産油国の減産延長計画を受け、原油供給ひっ迫への思惑から原油先物価格は上昇基調となった。
原油市場では、供給減少への懸念から原油先物価格が上昇基調を強めました。週末時点で北海ブレント原油先物は1バレル=72.40ドル、WTI先物は68.52ドルと、それぞれ週初から約2%高となり、年初以来最大の週間上昇幅を記録しました。これは米国が3月20日に発表した新たなイラン産原油取引制裁と、主要産油国による協調減産延長計画という二つの材料が重なったためです。
まず米政府は、中国の独立系製油企業(いわゆる「ティーポット」)を初めて制裁対象に含めるなど、イラン産原油の輸出取り締まりを強化しました。ANZ銀行の試算では、これによりイランの輸出が日量100万バレル減少し得るとの見方もあります。さらにOPECプラス(OPEC加盟国とロシアなど)の産油国グループは、現在の生産量が目標を上回っている状況を是正すべく、7カ国で追加減産を実施する計画を発表しました。具体的には4月以降、合計日量18.9万〜43.5万バレルの減産を毎月行い、2026年6月まで継続する内容です。
これら供給サイドの引き締まり要因により、エネルギー関連株が世界的に物色される展開となりました。石油メジャーや産油国の国営企業株はもちろん、シェールオイル企業などにも買いが波及しています。一方で原油高はインフレ要因でもあるため、輸入国のコスト増加や各国中央銀行の金融政策にも影響を与えかねません。投資家としては、今後の産油国動向(追加減産の有無や解除タイミング)や地政学リスクの高まりにも注意を払い、関連セクターへの投資判断を下す必要があります。
6. 中国、「特殊行動計画」で消費テコ入れ – 内需拡大へ政策総動員
中国政府は国内消費を活性化するための**「特殊行動計画」**を3月16日付で発表しました。国務院が全国の地方政府・部門に通達したもので、住民所得の増加や育児補助制度の創設などを通じて、消費能力を高め内需拡大を図るという内容です。近年、中国の個人消費はコロナ禍や不動産市場低迷の影響で伸び悩んでおり、需要喚起によってデフレ圧力に対抗する狙いがあります。
この行動計画には具体策として、都市・農村部の所得向上策や農民収入を底上げする住宅改革、さらには**「株式市場の安定化策を検討」**するといった項目も含まれました。もっとも、中央政府が号令をかけたものの、実際の財政出動や支援策の詳細については各地方政府の取り組みに委ねられており、「具体的な資金裏付けに乏しい」との指摘もあります。それでも李強首相が前週の全人代で内需拡大に重点を置く方針を示していたこともあり、中国当局の本気度が示された形です。
市場への影響としては、中国関連消費株(旅行・レジャー、小売、食品飲料など)に前向きな材料となりました。政府主導で可処分所得が増えれば消費回復が期待できるためです。一方で不動産やインフラ投資偏重から経済モデルを転換する難しさもあり、計画の実効性を見極める必要があります。投資家は、中国の小売売上高や消費者信頼感指数などが今後改善に向かうか注視しましょう。また計画に盛り込まれた株式市場安定策の具体策(例えば減税やIPO規制緩和など)が出てくれば、中国株全般にも追い風となる可能性があります。
7. ブラジル中銀、インフレ再燃で利上げ継続 – 政策金利10年ぶり高水準に
新興国ブラジルで、中央銀行が想定外の利上げ局面にあります。3月19日の金融政策会合で、ブラジル中銀(COPOM)は政策金利(Selic金利)を+1.00%引き上げ、14.25%としました。14%台の金利水準は2016年以来ほぼ10年ぶりの高さで、昨年末から100bp刻みの大幅利上げを3回連続で実施していることになります。昨年来就任したガリポロ新総裁の下、ブラジル当局は再燃するインフレに対し極めてタカ派的な姿勢を維持しているのです。
背景には、ブラジルの消費者物価上昇率が直近で5.06%と目標を上回り、1年ぶりの高インフレ水準に達していることがあります。加えてトランプ米大統領の通商政策が不透明感を増す中、レアル通貨安や輸入物価上昇のリスクにも備える必要が出てきました。ブラジル政府は物価抑制のため一部税制措置なども講じていますが、それでもインフレ期待を封じ込めるため中央銀行は独立性を保ちつつ果敢に利上げを続行しています。
この動きは新興国市場にも波及する可能性があります。利上げによってブラジル国内では景気減速の兆しも出始めていますが、高金利は海外からの資本呼び戻し効果もあり通貨防衛にはプラスです。一方で金利上昇に苦しむ国債市場や企業の借入コスト増大など副作用も無視できません。投資家にとっては、ブラジルをはじめとする新興国のインフレ動向と金融政策の行方が注目ポイントです。各国でインフレ抑制と景気下支えの綱引きが続く中、ブラジル中銀のように断固たる姿勢が奏功するのか、それとも景気失速を招くのかは今後数ヶ月で明らかになるでしょう。新興国債券や為替市場にも影響しうるため、グローバルポートフォリオを持つ投資家は要警戒です。
以上、2025年3月16日〜22日の週に株式市場へ影響を与えた主要ニュース7選でした。それぞれのニュースがマーケットに与えたインパクトと背景を押さえつつ、今後の展開を見極めることで、投資戦略のヒントにしていただければ幸いです。
無料メルマガ登録で投資初心者向けのお役立ち情報&私の実際の運用実績を公開中。
今すぐ証券口座を無料開設して、投資をスタートしませんか?